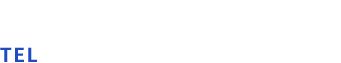決算特別委員会第2分科会
今日は「スポーツ推進本部」と「保健医療局」所管の決算審査が行われました。
①スポーツ推進本部
○パラスポーツ振興の取組
○スケートボードなどのアーバンスポーツの場の確保
○スポーツと健康増進について質疑しました。
以下、質問概要です。
【パラスポーツの振興の取組】
都が、本年3月に改定した「東京都スポーツ推進総合計画」は、「誰もがスポーツを楽しむ東京を実現し、一人ひとりのウェルビーイングを高め、社会を変革する」を基本理念とし、様々な達成指標を設定しています。
その一つに、障害のある都民のスポーツ実施率を2030年度に50%に引き上げるという目標があります。
目標達成に向けては、障害のある方が身近な地域で気軽にスポーツに親しめる機会を提供することが重要だと考えます。そこで、
(身近な地域におけるスポーツの場の確保について)
Q1,障害のある方のスポーツの場の確保に向けて、都はどのような事業に取り組んだのか、令和6年度の主な取組について実績を伺う。
A(パラスポーツ担当部長答弁)
〇 都は、特別支援学校の体育施設を活用して、身近な地域でのパラスポーツの場の充実を図っており、令和6年度は、障害の有無にかかわらず誰もが参加できるパラスポーツやスポーツ・レクリエーションの体験教室等を124回開催
○ また、行き慣れた場所で安心してスポーツを楽しめる環境を提供するため、障害者の日中の居場所である福祉施設等を対象に、障害種別などに応じた運動プログラムを定期的に実施し、運動習慣の定着を図る事業を18施設で計132回実施
都が、身近な地域でのスポーツの場づくりに積極的に取り組んできたことがわかりました。スポーツ施設だけでなく、特別支援学校や福祉施設などの身近な施設を活用することは、遠くまでの外出が難しい方やスポーツへの関心が薄い方にもアプローチできる有効な取組だと思います。
特別支援学校のスポーツ体験教室については、私は以前の質疑において、障害者が参加しやすい内容とするために、種目やルール、用具等について工夫していることを確認しました。
私は、教室参加のハードルを下げ、より多くの方にスポーツに親しんでもらうためには、時流に乗ったプログラムにするということも重要だと考えています。
いよいよ来月には東京2025デフリンピックが開かれます。大会開催はスポーツを始めるきっかけにもなると思います。
(デフスポーツ関連の特別支援学校体験教室について)
Q2令和6年度に開催した体験教室において、デフリンピックに関連した内容を何か実施したのか伺う。
A○(パラスポーツ担当部長答弁)
〇 令和6年度は、デフリンピックの気運醸成に向け、デフサッカー日本代表前監督によるトークショーや、音が聞こえない状態でサッカーを行い、音の有無が競技に与える影響を体感できる競技体験会を開催
〇 また、ろう学校では、デフスポーツに取り組むきっかけとなるよう、デフアスリートから直接指導を受けられる機会として、全4回の継続的なデフ卓球教室も開催
昨年度からデフリンピックに関連した体験教室が開かれ、気運醸成やスポーツを始めるきっかけとなるよう取り組んでいることがわかりました。
今年度もこの体験教室の場を活用して、トークショーや競技体験会が開催され、デフリンピック本番時にはパブリックビューイングも実施されると聞いています。ぜひ参加者に喜ばれるイベントを実施していただきたいと思います。
次に、運動習慣定着支援事業について確認します。
この事業は、都が福祉施設に指導者を派遣し、運動の習慣化や地域のスポーツ活動への参加につなげることを目指した事業だと聞いています。一つの施設につきその支援期間は1~2年だそうですが、重要なのは、都の支援が終了した後も、施設が主体的に運動に取り組んだり、また他の福祉施設にも波及していくことだと思います。
(運動習慣定着支援事業の事業効果について)
Q3,そこで、令和6年度の運動習慣定着支援事業で対象とした施設のうち、支援を終了した施設について、どのような成果があったのか、伺う。
A○(パラスポーツ担当部長答弁)
○ 令和6年度に都の支援が終了した施設に対し、先月アンケート調査を行ったところ、全ての施設において、指導者の派遣によって運動指導のノウハウを身に着けた施設職員などが中心となり、運動プログラムを継続
〇 また、各施設や自治体にヒアリングしたところ、施設内だけではなく、近隣のスポーツ施設に移動して運動を実施した例や、自治体のスポーツイベントに参加するようになった事例
〇 さらに、域内の福祉施設を対象に同様の事業を開始している自治体もあるほか、ボランティアとして参加した大学生が運動プログラムを継続してサポートするなど、障害者のスポーツの場の充実・定着につながっている
運動習慣定着支援事業の効果が、施設内での運動習慣の定着にとどまらず、自治体内で面的な広がりを見せ、成果が着実に表れていることがよくわかりました。
障害のある方のスポーツの場の充実を図ることで、障害のある方のQOLの向上のみならず、地域の様々な関係者の連携のネットワークが構築され、障害のあるなしに関わらず誰もが活躍できる共生社会の実現に寄与することが可能と考えます。ぜひ今後もパラスポーツ振興に向けた施策、特にこうした身近な地域のスポーツの場づくりに取り組んでいただくことを要望いたします。
【スケートボードなどのアーバンスポーツの場の確保】
東京2020大会では、新たに採用されたスケートボード競技において、日本は、五つのメダルを獲得、また、2024年パリオリンピックでも、メダル獲得数4つ、男子、女子ともに大活躍で日本中に大きな感動を与えました。
このように日本代表選手がスケートボードなどで目覚ましい活躍を見せ、若者を中心にアーバンスポーツの人気が高まっています。
アーバンスポーツは単に順位を競い合うだけでなく、参加者同士が互いのスキルを称えあったり、仲間や観客と一体となって楽しむ文化があるなど、コミュニティの形成や地域の活性化にも大きな期待が寄せられている。
一方、アーバンスポーツの盛り上がりに比して、活動できる場が不足しているのが現状であります。
Q1 アーバンスポーツが多くの人々から親しまれ、スポーツとして普及するためには、愛好者が安心してアーバンスポーツができる場所が必要と考えるが、都の取組について伺う。
A1(経営企画担当部長答弁)
○ アーバンスポーツを体験し楽しめる場として、昨年10月に有明アーバンにライブドアアーバンスポーツパークを開業
○ 開業イベントでは3×3バスケットボールなどの競技大会に加え、スケートボードの体験会も開催
○ 開業後は、アスリートの練習利用のほか、初心者を対象とした体験会や教室事業を展開し、昨年度は約半年で3万7千人の方にご利用
○ 利用者の意識啓発も同時に行っており、多くの方から親しまれるアーバンスポーツの普及に取り組んでいる
有明に開業したアーバンスポーツパークがトップアスリートだけでなく、初心者向けにも事業を展開し、多くの方々に利用されていることが分かった。また、マナーの意識啓発に引き続き取り組むことで、アーバンスポーツが多くの方に愛されるよう普及を進めていただきたい。
【スポーツと健康増進】
わが国では世界でも類を見ないスピードで少子高齢化が進行しており、これは東京都においても例外ではありません。このため、社会保障関係費は年々増加傾向にあり、これをいかに食い止めていくかが喫緊の課題になっています。そのためには、一人ひとりが、日頃から健康づくりに向けた取組をしていくことが大変重要です。
高齢者を対象としたある調査で、ウォーキングよりハードな運動(早歩きなど)を週3回以上継続している人は、運動習慣のない人(週1日以下)に⽐べて50%も認知症になりにくいとのデータが出ておりました。
また健常高齢者を対象とした研究では、運動習慣がない人は運動習慣がある人と⽐べて、認知症になるリスクが1.82倍であることも報告されておりました。
更なる高齢化を見据えた場合、シニアになってから運動するのではなく、働き盛り世代のうちから運動習慣を定着させることで、将来の介護や認知症のリスクを低減させていくことが重要です。
(スポーツを通じた健康増進事業について)
Q1,都は、都民の健康づくりに向けて「スポーツを通じた健康増進事業」を行っているが、昨年度の事業内容について伺う。
A○(スポーツ担当部長答弁)
○ 都は、 運動能力測定を契機に、都民の健康への関心を高め、継続的なスポーツ実施につなげていくことを目的に、令和6年度からスポーツを通じた健康増進事業を開始
○ 具体的には、握力、反復横跳びなど6種目の測定を実施した上で、測定結果に基づき健康に対する意識の向上、運動習慣の定着につながるアドバイスを実施
○ 昨年度は、幅広い年代の方々を対象に、六本木ヒルズアリーナでキックオフイベントを行ったほか、自治体等のイベントと連携し、1,000人以上の参加者に体力測定を実施
体力測定を通じた健康増進の取組を、引き続き、若年層や働き盛り世代を含めた、健康づくりの取り組みを進めていただきたいと思います。
一方で、都による取り組みを一過性に終わらせることなく、健康に対する意識の高まりを継続的な運動習慣に結び付けていく必要があります。そのためには、都は区市町村と連携し、身近な地域における運動機会の創出に取り組むことが重要であると考えます。
(ソフト補助について)
Q2,区市町村が行うスポーツ振興の取組に対し、都はどのような支援を行ったのか、また参加者からどのような意見があったのか伺う。
A2(スポーツ担当部長答弁)
○ 都は、区市町村が実施するスポーツ振興事業等の経費に対し、原則として300万円を上限に、3分の1を補助
○ 昨年度は、区市町村が独自に実施した住民向け体力測定や、ウォーキング大会など、地域のスポーツイベント等の開催を支援
○ 例えば、地域のスポーツセンターで開催された体力測定では、参加された方から、「改めて継続的な運動習慣が大切であることを感じた」等の声があったと聞いている。
都が区市町村のスポーツ振興の取組を幅広く支援していることがわかりました。忙しい日常の中で、誰もが気軽にスポーツに親しむためには、身近な地域における機会の確保が大変重要です。都民のスポーツの習慣化を促進し、健康づくりにつなげていくためにも、区市町村の取組を引き続き支援していただきたいと思います。
私の地元、世田谷では、スケートボードが盛んに取り組まれており、地元愛好者の方々の熱意によって、都立駒沢オリンピック公園や区立公園内にスケートボードパークが整備されました。
私も度々現地を見学させていただいていますが、週末などは大変な混雑となることも少なくありません。このようなニーズに応え、スポーツの気運を一層高めていくためには、身近な地域でのスポーツの場の確保が重要です。
(ハード補助の事業内容について)
Q3,そこで、区市町村のスポーツ施設の整備に対し、都はどのような支援を行ったのか伺う。
A(スポーツ担当部長答弁)
○ 都は、区市町村が、地域のニーズに応じてスポーツ施設等を整備する場合、これに係る経費について、1施設あたり
5,000万円を上限とし、原則として2分の1を補助
○ 昨年度は、アーバンスポーツの実施場所の創出としては、使用しなくなった市民プールをスケートボード等ができる場に改修する工事に支援
誰もが身近な場所でスポーツに取り組める環境を確保していくためには、こうした地域の取組が重要であり、一層の支援を求めます。