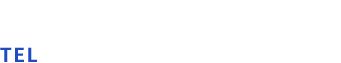決算特別委員会第二分科会
今日は福祉局の決算審査が行われました。
質問は
○認知症サポート検診事業
○里親等委託の推進
○ベビーシッター利用支援事業
○重症心身障害者等のショートステイの拡充
○居住支援特別手当
について質疑を行いました。
以下、質問概要です。
【認知症サポート健診事業について】
平均寿命が延び、高齢化率の高まる今日において、認知症は誰もがなる可能性があります。
東京都の認知症人口は、2025年には約56万人(65歳以上の約17%)に増え、そのうち見守りや支援が必要な方は約42万人に達するとされています.
また、認知機能の低下した方の63%はご自宅で生活し、さらにその16%は一人暮らしであるとされています(平成26年東京都調査)。
認知症支援を医療や介護の専門職だけでなく地域全体で考えていくことが求められます。
○目的
認知症に早くきずき、早期に診断を受けることは重要であります。
早めに治療すれば改善が可能な病気を見つけたり、症状が軽いうちに今後の生活の準備をしたりすることができます。
認知症の方を早期診断につなげるには、まず、検診を受けていただくことが必要であり、都は、東京都認知症施策推進計画における基本的施策の一つとして認知症の早期のきずき・早期診断・早期支援を掲げ、その取り組みとして認知症サポート検診事業を実施している。
Q1,認知症サポート事業の目的と検査の対象年齢や補助率も併せてその内容を伺います。
○本事業は、認知症の早期診断・早期支援を目的としており、
都は、区市町村が実施する事業の経費を補助
【補助率】10/10で、区市町村に対しては手厚い補助をしているとのこと、ぜひとも多くの区市町村で活用し、一人でも多くの方に検診を受けていただきたいと思います。
Q2,令和6年度の区市町村による補助の活用状況と、本事業で認知機能検査を受信した人数についても併せて伺う。
本事業における認知機能検査には、医師の判定が必要とされている。
ある自治体では、検査会場で判定する医師の確保が難しく、本事業の活用に躊躇しているとの意見もありました。
事業の目的からすれば、区市町村が利用しやすいように取り組むべきと考えます。
Q3,本事業を活用する区市町村が認知機能検査をどのように実施しているのか伺う。
あわせて、医師の確保が難しいという区市町村に対して、都としてどのような支援を行っているのか伺う。
25区市町で合計12000人が認知機能検査を受信
本事業は原則として50歳以上の都民が対象とのことですが、
区市町村によっては、70歳と75歳に限定だったり、65歳から5歳刻みの自治体もあります。
ある自治体では、より大規模な形で住民を会場に集めて、普及啓発、認知機能検査を行いたい意向があると聞いております。
そういった取り組みであっても、この事業を活用できるよう、都は区市町村の意向を丁寧に聞きながら柔軟に対応していただきたい。
【里親等委託の推進】
次に里親等委託の推進について伺います。
社会的養護の必要な子どもは全国で約42000人、東京都では約4000人おります。
「新しい社会的養育ビジョン」では、未就学児の里親等委託率を75%以上、学齢期以降は50%以上にする目標に対し、令和4年度末の全国平均では24.3%。東京都では17.2%の水準です。
Q1,里親等委託率が伸びない理由と、令和6年度の取組について伺う。
【子供・子育て支援部長答弁骨子案】
○ 里親登録数の拡大に向けて、里親制度の社会的な理解の促進や、認知度の更なる向上が必要
○ 実親の同意取得が困難であるため委託に至らないケースも存在
○ ケアニーズが高く対応が困難な児童への対応のため、里親の養育力向上や里親に寄り添った支援が必要
○ こうした現状を踏まえて、令和6年度は、養育家庭体験発表会等の普及啓発の他、里親支援を包括的に行うフォスタリング機関事業を順次拡大して実施
都は、本年3月に新たな「東京都社会的養育推進計画」を策定、令和11年度までの5年間取り組んでいくこととなった。
計画では、「家庭養育優先原則」と「パーマネンシー保障」の2つの考え方に沿って、社会的養護の下で育つ子供たちについて、家庭と同様の養育環境において、健やかに育ち、自立できることを目指すことを基本理念の一つに掲げている。
Q2, 「家庭養育優先原則」と「パーマネンシー保障」の考え方について、見解を伺う。
【子供・子育て支援部長答弁骨子案】
○ 子供の最善の利益を実現するためには、「家庭養育優先原則」と「パーマネンシー保障」の考え方に基づく支援が必要
○ まず、予防的支援により、家庭での生活を維持する努力が重要
○ 代替養育が必要な場合でも、子供の意向や状況等を踏まえながら、できる限り家庭と同様の環境での養育を目指す
○ 「育ちの連続性の保証」の観点から、支援の主体が変わっても、子供中心の途切れないケースマネジメントが必要
「家庭養育優先原則」と「パーマネンシー保障」の考え方を伺いました。
Q3,東京都社会的養育推進計画における取組の方向性について伺う。
【子供・子育て支援部長答弁骨子案】
○ 都は、社会的養育推進計画に基づき、家庭における養育が困難な場合でも、家庭と同様の環境で養育できるよう、里親等委託を推進
令和11年度における里親等委託率37.4%を目標
○ 計画では、里親制度の普及と登録家庭数の拡大を進めて里親等への委託を促進、里親に対する支援を充実、特別養子縁組に関する取組を推進の3つの方向性
私は昨年の決算特別委員会で里親等委託の推進について質疑を行いました。
里親委託の推進に当たっては、里親制度の周知や理解促進のための養育家庭体験発表会や、里親支援を包括的に行うフォスタリング機関事業を実施しているとの答弁であった。
〇 児童相談所において、施設入所児童の里親委託を検討するため、児童の意向確認や実親の同意を得るための丁寧な説明、関係機関と連携したフォロー体制を整えるなど、里親委託を優先したケースワークを推進していくとの答弁もあった。
様々な普及啓発や、児童相談所のケースワークにより里親委託を進めていくとのことだが、現在の委託率をみると充分ではない。
Q4,計画に定めた取組の方向性を一層進めていく必要があると考えるが、具体的な取組について伺う。
【子供・子育て支援部長答弁骨子案】
○ 今年度、民間企業に対する説明会を新たに実施するなど、広報・普及啓発の取組を拡充
○ 乳児院に、養親希望者と養子候補児童の交流、マッチングなどを行う専任職員を新たに配置するなど、乳児院の体制強化
○ 計画に定めた取組の方向性を一層進めるため、現在、児童福祉審議会専門部会において、具体的な論点と課題を踏まえて現在検討
【ベビーシッター利用支援事業の一時預かり利用支援について】
日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者が、ベビーシッターを利用する場合の利用料について、
区市町村が負担軽減を行う場合、その費用の一部を補助することにより、保護者の多様なニーズに応えるとともに、ベビーシッターを安心して利用できる環境を整備するものです。
Q1,ベビーシッターによる一時預かりを利用するという家庭が増えてい
る。過去3年間のベビーシッターによる一時預かり利用支援の実施自
治体数と利用児童数の実績を伺う。
【担当部長答弁骨子案】
○ 令和4年度が14区市8,424人、5年度が19区市16,70
4人、6年度が26区市27,275人
ひとり親や、低所得の方が利用料を一時的に立て替えるのが大変で、ベ
ビーシッター利用を諦めざるを得ないケースがあるとの相談を頂く。
(利用料は一時間当たり、日中預かりで2500円、夜間利用では3500円)
Q2,ベビーシッター利用者の経済的負担を軽減させるために、利用者が立
替払いをしなくても済むような仕組みに切り替えるべきと考えるが、
見解を伺う。
【担当部長答弁骨子案】
○ 本事業では、ベビーシッターを利用した保護者が、利用料を一旦、
立替え、区市町村から助成を受ける仕組みとなっているが、申請方法
等は区市町村によって様々
○ 今後、保護者への助成に係る課題等を整理するため、区市町村や事
業者への意見聴取を通じて実態を把握
【重症心身障害者等のショートステイの拡充】
重症心身障害者等のショートステイ、短期入所は、在宅で障害児者を介護、療育されている家庭にとっては、病気のとき、あるいは何かご都合があってどうしても外出しなければならない時、在宅生活を送るうえで欠かせない支援です。
【短期入所について】
私は、重症心身障害児等やその家族の在宅生活を支える短期入所の充実について、令和5年の予算特別委員会で取り上げた。
局からは、短期入所をさらに拡充するため、病院等への支援や事業実施の働きかけを実施するとの答弁があった。
令和5年度からは、医療型短期入所開設支援事業を開始し、民間のノウハウも活用しながら短期入所の拡充に向けた取り組みを行っていると聞いている。
Q1そこで、具体的な取り組みと令和6年度の実績について伺う。
○資源が不足している地域を中心に病院・介護老人保健施設など計50か所を訪問
○開設に興味のある病院等を対象に、新規開設に向けた説明会を実施
○検討している施設を対象に、既実施施設での利用者受入・退所時の見学や懇談会等を実施
○新規開設した病院等を対象に、個別にフォローアップと実践的な研修を開催
重症心身障害者等とその家族にとって短期入所は、在宅生活を送る上で欠かせない支援
家族の休養等支援し、重度障害児者等の健康と家族の福祉の向上を図るため、医療ニーズに対応可能なショートステイ事業をより一層促進してほしい
【居住支援特別手当】
都議会公明党は令和5年第4回定例会の代表質問で、介護職の低賃金が一つの要因として、介護人材の不足が大きな課題となっている中、都独自の支援策を講じていくよう求めました。
こうした提案を受け、都は令和6年度より介護職員・介護支援専門員、並びに障害福祉サービス等職員を対象とした居住支援特別手当が創設され、都議会公明党にも喜びの声を頂いているところであります。
Q1 はじめに、令和6年度から開始した居住支援特別手当について、これまでの成果をお伺いします。
A1(高齢者施策推進部長)
○都は、令和6年度から、国が介護報酬等について必要な見直しを講じるまでの間、福祉・介護職員を対象に、居住支援特別手当を支給する事業者を支援。
〇令和6年度は、介護分野では、約1万5千事業所の約8割が申請。障害分野では、介護事業所を併設する事業所介護部門でまとめて申請する事例もあり、約1万5千事業所のうち、申請したのは約5割。
〇介護・障害分野をあわせ、約5000法人へ281億9千万円を補助。
多くの事業者が活用しているということですが、申請していない事業者も高齢分野では約2割、障害分野では約5割いるとのことであります。
介護職従事者の方より、所属する事業所が居住支援特別手当の申請をせず、せっかくの事業にもかかわらず私たちに支援が行き届かず大変に困っているとの声も寄せられております。
評価の高い事業でありますので、都内全ての事業者が活用できるよう、取り組んでいくべきと考えます。
Q2 本年3月の予算特別委員会の都議会公明党の質疑において、都は、本事業の申請に当たっての課題を把握するため、全事業者にアンケート調査を実施するとの答弁があったところですが、その結果についてお伺いします。
A2 (高齢者施策推進部長)
〇本年6月に、アンケートを実施し、約1500法人から回答。
〇申請手続きのサポート、事業の周知・説明を希望する事業者が多かった。
行政手続きなどの申請においては、ともすれば煩雑になりがちで労力を要し、申請が敬遠されてしまっているケースもあるのではないかと思います。
申請手続きのサポート、事業の周知・説明を希望する事業者が多かったとのことでもあり、こうした点を改善することによって活用が促進されるものと考えます。
Q3 アンケート調査により把握した課題を踏まえ、今後、申請率向上に向けて積極的に取り組んでいくべきと考えますが見解をお伺いします。
A3(高齢者施策推進部長)
〇本年8月から、未申請の全事業者に対し、コールセンターからプッシュ型で本事業の周知を図っている。
〇申請意向があり、手続きのサポートを希望する事業者に対しては伴走型できめ細かく支援。
〇さらに、本年6月から、都のホームページで手当を支給する事業者の公表を開始。
〇本事業の更なる活用を進め、介護職員等の処遇改善につなげていく。
都独自の制度として、喜ばれ期待されている事業でもありますので、是非今後ともより多くの事業所で活用され、介護や障害福祉の最前線で働かれている皆様に支援が行き届くよう積極的な取り組みをお願いいたします。