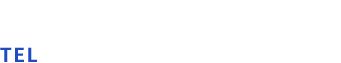総務委員会が行われ、質疑を行いました。
◎監査事務局
◎選挙管理委員会事務局
◎デジタルサービス局
◎スタートアップ・国際金融都市戦略室
私はデジタルサービス局所管で
①オープンローミング対応Wi-Fiについて
②デジタルデバイドについて
③サイバーセキュリティ対策について
それぞれ質疑を行いました。
デジタルを活用した様々なサービスを都民が便利に利用するためには、その基盤となる通信環境の整備が重要である。都は昨年度、「つながる東京展開方針」を策定し、安全で利便性の高いオープンローミング対応WiFiについて、都有施設や区市町村施設への整備を進めてきた。
私の地元である世田谷区でも、駒沢オリンピック公園などへの整備が進み、利用環境が整ってきたところである。都有施設は着実に整備が進んでいると思うが、住民にとって一番身近な区市町村施設のWiFi整備も重要である。
Q1
今年度から開始した区市町村への支援状況と今後の取組について伺う。
A1(つながる東京整備担当部長答弁)
〇 都は、今年度から、区市町村施設へのオープンローミング対応WiFiの導入を促進するため、設置済みのWiFi設備の切替に対する財政支援や、伴走型の技術サポートを開始
〇 これまで、7自治体175か所の整備に対し補助を行うとともに、通信環境整備に不慣れな区市町村職員をサポートするため、仕様検討に必要な現地調査や計画図面の作成など、整備に直結する技術支援を7自治体で実施
〇 来年度は、既存設備の切替に加え、新規にWiFiを設置する際の費用についても補助対象とすることで、区市町村への支援を拡充し整備を加速
都が財政措置を含め、区市町村を伴走型で支援し、区市町村施設へもオープンローミング対応WiFiの整備が広がってきたことを確認できた。
Q2
安全で利便性の高いオープンローミング対応WiFiの整備が進んできているが、整備を開始した昨年度から、現在までの利用状況の推移を伺う。
A2(つながる東京整備担当部長答弁)
〇都有施設638か所への整備が完了した令和5年度末時点では、月当たりのアクセス数は約175万回
〇今年の1月末時点では、都有施設等約830か所で整備が完了しており、月当たりのアクセス数は約700万回。昨年度末と比較して、約4倍の利用状況
WiFiの整備が進捗するとともにアクセス数も伸びており、利用者のニーズが高いことがわかった。引き続き、オープンローミング対応WiFiの整備を着実に進めていって欲しい。
これまで都有施設などの公共施設への整備を進めているが、災害を想定した場合、通信を必要とする場所は、屋外の対応も必要である。帰宅困難者対応などでも、オープンローミング対応WiFiが利用できる環境を整備することが必要である。
そこで、
Q3
オープンローミング対応WiFiを都有施設に着実に整備するとともに、屋外の人が多く集まる場所にも整備を拡充すべきと考えるが、来年度の取組を伺う。
A3(つながる東京整備担当部長答弁)
〇 整備を必要とする都有施設については、来年度約300か所に設置を行い、概ね完了する予定
〇 これに加え、来年度は災害時にも人が多く集まる主要駅周辺や公園など、屋外への整備も開始する。電話ボックス等の民間アセットを活用し、約600か所に設置
〇 今後、計画的に取組を進め、令和7年度からの3年間で約1,800か所への整備を推進
災害対応等を想定し、都が更なるWiFi整備に踏み出すことを高く評価する。オープンローミング対応WiFiを様々な場所で利用できるようになっており、今後は、利用者が通信サービスを快適に利用できるようにすることも肝要である。現在、街なかで利用されているWi-Fiの中には、通信速度が遅く、途中で接続が切れてしまうものも多い。
そこで、
Q4
都が整備を進めるオープンローミング対応WiFiは、高品質な国際規格だと聞いているが、通信品質の確保にどのように取り組んでいくのか伺う。
A4(つながる東京整備担当部長答弁)
〇 都のオープンローミング対応WiFiは、一度設定すれば、セキュアでシームレスに接続できる高品質なWiFiである
〇 来年度は、さらなる通信品質の向上に向け、通信速度や電波強度について基準値を新たに設け、設置後も通信速度調査や接続状況の監視を行い、利用者にとって快適な通信環境を提供できるよう継続的に取組を実施
引き続きオープンローミング対応Wi-Fiの整備を展開し、利用者にとって快適な通信環境の提供を進めていっていただきたい。
(サイバーセキュリティ対策について)
次に、サイバーセキュリティ対策について伺う。
サイバー攻撃は高度化しており、先日も世界的に利用されるSNSである「X」が一時サービス停止した。これは、特定のサーバに一度に処理能力を超える大量のデータを送りつけ、サービスを不能にする、いわゆるDDоS攻撃が原因とされている。こうしたサイバー攻撃はいつ何時起こるか予測できないことから、一層の備えが必要である。
こうした中、都は、1月末に公表された「シントセイX」の素案の中で、来年度新たにサイバーセキュリティセンターを立ち上げることを明らかにした。国も巧妙化するサイバー攻撃に対する対策強化を進める中、日本の首都である東京が新たな対策に取り組むことは期待も大きいものと考える。
Q1
まず、サイバーセキュリティセンターが果たす役割について、伺う。
A1(情報セキュリティ担当部長答弁)
○ 高度化、巧妙化するサイバー攻撃から都民の重要情報や、都民生活を支える重要インフラなどを防護するためには、全庁的にセキュリティ対策を強化することが重要であることから、来年度、司令塔となるサイバーセキュリティセンターを立ち上げ、一元的な対策を実施
〇 センターでは、GovTech東京の専門人材の知見をもとに、これまでの対策に加え、来年度新たなセキュリティツールを順次導入し、システム機器の脆弱性を網羅的に把握し、攻撃を未然に防ぐための対策を行う
〇 センターが把握した各局の個別システムの脆弱性に対して、技術的な見地から具体的な対応をきめ細かく支援することで、全庁のセキュリティレベルの向上を図る
サイバーセキュリティセンターが全庁の司令塔となり、さらなる対策の強化を進めていくということが分かった。
私は令和6年の事務事業質疑において、GovTech東京のエンジニアと連携し高度化するサイバー攻撃に対応することを求めた。
Q2
サイバー攻撃は早期に検知し対処することが重要であり、GovTech東京の技術力を生かして対策を進めていく必要があるが、どのように取り組むのか伺う。
A2(情報セキュリティ担当部長答弁)
〇 これまでも、各局でインシデントが発生した際、GovTech東京と連携し、被害拡大防止のための初動対応や復旧対策、再発防止策をきめ細やかに支援
〇 さらに、センターの立ち上げを機に、これまで各局で個別に監視していたシステムやネットワークの通信ログを一元的に集約する。GovTech東京の技術力を活かし、より高度な分析を行うことで、攻撃の予兆を早期に捉え、予防的な対策につなげる
GovTech東京のエンジニアによる技術的な支援のもと、セキュリティ対策を一層強化してほしい。
サイバー攻撃を受けた際、職員一人一人の対応が重要となることから、昨年の事務事業質疑では、研修・訓練の重要性を確認した。
都は本年1月、新たに重要インフラへの重大な攻撃を想定した、危機管理対応訓練を行ったと聞いている。
Q3
重要インフラを対象とした今回の危機管理訓練の成果と来年度の対応について、伺う。
A3(情報セキュリティ担当部長答弁)
○ 本年1月、都立病院でランサムウェア被害により電子カルテシステムが停止し、医療提供ができなくなった事態を想定した実践的な危機管理訓練を実施した。都の最高情報セキュリティ責任者であるCISO,関係局長等が参加し、初動対応を中心に演習形式で実施
〇 訓練では、対応方針の決定で重要となる正確な情報収集、共有や、被害の拡大防止及び早期復旧に向けた現場への支援などの重要性を確認
〇 来年度は、都庁グループ全体の情報共有ツールの共通化や現場の支援体制の強化等の対策を行う。また、対策の実効性を訓練で確認するとともに、他の重要インフラにも対象を拡大し、内容を充実し、訓練を積み重ねることでサイバー攻撃発生時の対応力を高める
サイバーセキュリティに関する訓練・教育について、来年度も対策を進めることが確認できた。
引き続き、万全の備えをお願いしたい。