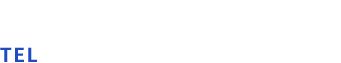今日も総務委員会が行われ、質疑を行いました。
私は総務局所管で
①東京都のグローバル専門人材の育成
②トイレ防災マスタープラン
③富士山噴火降灰対策
④避難所運営指針素案におけるペットの受入体制
について、それぞれ質疑を行いました。
【トイレ防災マスタープラン】
東京都では2月に新たに「トイレ防災マスタープラン」の素案を公表。
マスタープランでは、首都直下地震の被害想定を踏まえ、災害時のトイレ確保の主体となる区市町村を支援するために策定する計画を示しました。
これまで都議会公明党は、能登半島地震などの過去の災害の教訓を踏まえ、災害時におけるトイレ環境の確保・整備が重要であることから、災害時のトイレ対策について質疑を重ねてきたところである。
都が、区市町村の指針ともなる、トイレ防災マスタープランを策定し、さらに補助制度を創設したことは評価いたします。
来年度実施される補助事業では、トイレカー・トイレトレーラーなど含め、様々な種類のトイレが対象になっています。
災害用トイレについては、状況に応じて様々な組み合わせが必要です。
Q5,区市町村がマンホールトイレや携帯トイレなどについて、いざ災害時となっても、それらのトイレがきちんと利用できるようにしておくとともに、災害時のみならず平時から活用できるフェーズフリーのトイレについても普及させていくべきと考えます。見解を問う。
【富士山噴火降灰対策について】
富士山の大規模噴火が発生した場合の降灰については、都内の広範囲に及び、また、エリアにより、降灰(こうはい)厚(あつ)などの状況が異なることが想定される。
このため、発災時に道路除灰などの応急対策を迅速に進められるよう、都内の降灰状況を計測し、その情報を集約するための体制を、あらかじめ構築しておく必要がある。そこで、
Q1(降灰状況の把握)
降灰状況を把握するための各主体の役割分担や取組について、伺う。
A1(担当部長答弁案骨子)
〇 都は、本年2月に公表した地域防災計画火山編修正素案において、降灰厚情報等の把握・収集の役割分担や対策の内容を定めた
〇 庁内各局や区市町村等が降灰の厚さ等について、地上調査、東京都災害情報システムに入力することで、総務局が降灰状況を集約し、関係機関と情報共有
〇 今後、システムの再構築を予定しており、改修後は降灰情報を地図上に視覚的に表現できるようになる
〇 来年度から降灰の計測方法や調査場所、情報の集約方法等について、関係機関との調整を行っていく
いつ起こるとも知れない大規模噴火に備え、降灰状況の把握のための体制整備を進めてほしい。
交通インフラや通信等のライフラインが発達した現代社会において、大規模な降灰が生じた事例は少ない。
とりわけ富士山については、前回の噴火から300年以上が経過しており、実際に大規模噴火が発生した場合、道路や鉄道の状況や復旧見込み、取るべき対応等について、不安を感じる都民も多いと思う。そこで、
Q2 (発災時の情報発信)
災害状況については、除灰等の応急対策を行う関係機関への情報共有に加えて、都民等に対しても正しい情報が届くよう、発災時の情報発信を積極的に行うべきと考えるが、都は、どのように取り組むのか、伺う。
A2(担当部長答弁案骨子)
〇 都は、気象庁や報道機関等と連携し、降灰の状況や想定される健康への影響と対策など、発災時に正確な情報を届けていくこととしている
〇 具体的には、SNSや防災アプリ、Lアラートなど、様々なツールを活用し、災害の状況に応じて適切に情報発信
災害時にも、都民が落ち着いて行動できるよう、発災時の情報発信体制の強化に積極的に取り組んでほしい。
富士山の大規模噴火時には、最悪のケースでは、約1.2億㎥の降灰が発生することが想定されることから、火山灰の除去作業後、一時的に集積する仮置き場を確保するなど、火山灰の都市機能の早期回復に向けた迅速な降灰処理が必要である。そこで、
Q3(富士山噴火に伴う火山灰の仮置き場の確保)
昨年十月の分科会で、条件に合う場所を候補地とするとの答弁があった。火山灰の仮置き場の確保に向けて、都は、どのように取り組むのか、伺う。
A3(担当部長答弁案骨子)
〇 秋以降、計画の火山編修正素案を策定していく中で、火山灰の仮置き場の候補地の選定の基準について定めたところ
〇 具体的には、公有地等を抽出した上、概ね100㎡以上の一定の面積を有し、ダンプやトラックが搬入可能な出入口があること等の条件を満たすことや、傾斜地や河川・水路近傍の場所の除外を基準とした
〇 今後、この基準を踏まえ、区市町村と調整を始めることとしている
火山灰の仮置き場について、今後、区市町村との調整を始めるとのことであるが、最終処分場についても、役割分担や手順等を具体化していく必要がある。
一方、国が火山灰の取扱い等について、明確な指針を示していないとのことなので、引き続き、国に対し、早急に指針を示すよう、要望してほしい。
【避難所運営指針素案におけるペット受入体制について】
総務局ではこのほど、災害時の避難所の生活改善に向けて、避難所運営指針の素案を取りまとめました。
この指針は
〇東京都における避難所の将来のあるべき姿(都が目指す避難所の基準)とともに
〇都・区市町村において、直ちに取り組むべき具体的な取組をガイドラインとして提示するもの
今までの大規模震災での避難所の課題で、ペットの受け入れ体制については
ペットの受け入れ環境や準備が不十分なため、ペット飼養者(しようしゃ)が不自由な車中泊やテントでの避難生活を強いられてもおりました。
今回の素案では
「ペット飼育者が安心して避難できる環境が整っている」ことを目標とし、
「全ての避難所でペット受け入れ体制の確保」を基準とするとしています。
これまでのペット同行避難としていた考え方を「同行避難」と「同伴避難」に分けて記載することになりました。
ペットを飼育している都民にとって、「同行避難」「同伴避難」という用語が具体的にどのようなものなのか、まだまだ、理解されていないと考えます。
Q1
「同行避難」と「同伴避難」それぞれの定義と、今後、それらの定義をどのように周知していくのか、伺う。
A1(避難所・物資担当部長答弁骨子案)
〇 令和6年11月内閣府が出した「避難所の現状・課題について」によると、ペット同行避難とは、ペット飼育者がペットとともに、避難所など安全な場所に避難する行動のことであり、ペット同伴避難とは、災害の発生時に、飼い主が同行避難したペットを避難所などで飼養管理する状態を指す。ただし、避難所などで飼い主がペットを同室で飼養管理することを意味するものではないとされている。
〇 こうした内容を指針に明記するとともに、来年度はこれらの定義を含め、ペット同行・同伴避難の重要性を東京都防災ホームページなどを活用して周知
次に、避難所でのペット受入れ体制の整備について伺います。
避難所運営を円滑に行うための手段として、避難所ごとに作成するマニュアル
に、その地域の実情に応じたペット受入れの取組事項が盛り込まれ、受入れ体制の整備が着実に進むようにすべきと考える。
世田谷区のある避難所の開設・運営訓練を参加した際、その避難所
の運営マニュアルには、避難所でのペット受入れの際の留意事項などが、はっき
りと明記されていました。
しかし、都内全体を広く見るに、各避難所における運営マニュアルの作成、そ
してマニュアルへのペットの受入れに関する取組事項の記載が、避難所に
よってまちまちなところがあるかと認識いたします。
Q2
今後、各避難所の運営マニュアルへの避難所でのペット受入れの取組事項がしっかりと記載されるよう、どのように取り組んでいくのか、伺う。
A2(避難所・物資担当部長答弁骨子案)
〇 素案では、ペットを避難所に受け入れるための滞在場所の設置、ペット滞在ルールを作成・確立など、避難所で取り組むべき事項を盛り込み
〇 来年度は、都が策定する指針を区市町村に丁寧に説明するなど、避難所のマニュアルに反映されるよう取り組んでいく。
次に、区市町村の避難所におけるペット同行・同伴避難受入れの支援について
伺う。
Q3
都として、今後、区市町村の指定避難所でのペット受入れ体制の整備を進めるにあたって、どのような支援を行っていくのか、伺う。
A3(避難所・物資担当部長答弁骨子案)
〇 都は、来年度、専門家によるセミナー開催などに加え、同伴避難に必要なケージなど資機材の整備を進められるよう、新たな補助金を創設し、区市町村の取組を支援していく。