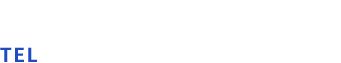決算特別委員会第2分科会
今日は「スポーツ推進本部」と「保健医療局」所管の決算審査が行われました。
②保健医療局
○下水道サーベイランスの活用
○がん診療連携拠点病院等でのがん相談の充実
(就労支援に対する社会保険労務士等の活用)
○骨粗しょう症の検診
○都立病院の経営
○民間地域病院への支援
○薬物乱用防止の取り組み
について、それぞれ質疑を行いました。
以下、質問概要です。
【下水サーベイランスの活用】
近年、人、モノの移動がグローバル化していることなどに伴い、世界の各地で発生する新たな感染症が国境を越えて広がっています。
このような中で、下水中のウイルスを検査、監視する下水サーベイランスという手法は、受診行動や検査数等の影響を受けることなく、無症状感染者を含めた感染状況を反映する客観的指標として活用が期待をされております。都議会公明党は、これまでの定例会や委員会で、下水サーベイランスへの迅速な対応を求めてきたところです。
○2020年、新型コロナウイルス感染症が、世界中に感染拡大しました。
新型コロナウイルス感染症は五類移行後も、毎年夏と冬には感染者数の増加が見られており、引き続き注意をしていく必要がある。
○一方で、患者数が定点把握になったことから、受診行動や検査数等の影響を受けることなく、無症状感染者を含めた感染動向の把握を補完する手法として、下水サーベイランスの活用が期待されている。
Q1,これまでも、都議会公明党より下水サーベイランスの活用を求めてきたところだが、まずは令和6年度の都の取組を伺う。
(部長答弁案 骨子)
下水サーベイランスは、地域の感染状況を把握する手法の一つであり、都は令和2年度から、下水を活用した調査を試験的に実施
昨年度、国は、下水サーベイランスを感染症流行予測調査に位置付けたことから、都は、これに基づく調査を都内1か所で開始し、国に報告
○国の流行予測調査に基づき、着実に取組を進めていることは分かった。
○都はもともと人口が多いことに加え、通勤・通学や観光などで都内を訪れる方も多い。都内の感染状況を、より詳細に分析し、情報発信することで、下水サーベイランスを感染防止に役立てることが期待される。
Q2,都として、下水サーベイランスを積極的に進めていくべきと考えるが、現在の取組状況について伺う。
(部長答弁案 骨子)
今年度、都は、国に報告している1か所を含めた、都内全20か所の水再生センターを対象に、国の実施要領を踏まえた調査を実施
健康安全研究センターでは、令和5年度、令和6年度の下水サンプルを保存しており、全20か所の水再生センターを対象に、さかのぼって分析
今後、東京iCDCの専門家から助言をいただきながら、都民や関係機関等に対する情報提供の方法を検討
○全20か所、令和5年度までさかのぼって調査をしているということ、また、東京iCDCの専門家の知見も活用するということで、都独自の取組を進めていることが分かった。
○新型コロナウイルス感染症だけでなく、新たなパンデミックへの備えとしても、下水サーベイランスは期待されている。
○データ公表に向けて、引き続き着実に取組を進めていただきたい。
【がん診療連携拠点病院等でのがん相談の充実】
<就労支援に対する社会保険労務士の活用について>
国立がんセンターの統計によれば、一生のうちにがんと診断される確率は、男性で65.5%、女性で51.2%。日本人の2人に1人以上ががんになるという数字は、もはや誰にとっても、がんを他人事と切り捨てることができない時代の到来を示すものとなった。
また、社会的にも、がん患者の治療と仕事の両立の必要性への認識も高まっており、社会保険労務士等を活用した就労支援の取組は重要と考えます。
私の地元の世田谷区でも定期的にがん患者等就労相談会を実施しております。
がん患者の方が仕事を続ける上で抱える不安や様々な問題について、看護師・社会保険労務士がお話をうかがい、一緒に考え、問題解決のお手伝いをします。
Q1,そこで、がん診療連携拠点病院等における就労支援の取組の現状について伺います。
【医療改革推進担当部長答弁骨子案】
A1
〇 がん診療連携拠点病院等では、がん相談支援センターにおいて、治療と就労の両立に関する相談を実施
〇 都は、がん診療連携拠点病院が、社会保険労務士等を配置して就労に関する相談支援を実施する場合、必要な経費を補助
〇 令和6年度は、38病院中21病院で、個別相談会や就労支援セミナーを開催
Q2、今後、社会保険労務士等の活用を積極的に進めるべきと考えますが、都の取組について伺います。
【医療改革推進担当部長答弁骨子案】
A2
〇 都は、これまで、がん患者が不安なく治療と就労の両立ができるよう、社会保険労務士等の活用による就労支援を推進
〇 今年度は、新たに東京都がん診療連携協議会において、がん診療連携拠点病院を対象に、社会保険労務士等の活用を働きかけ
〇 今月末には、協議会の相談・情報部会担当者連絡会において、社会保険労務士の役割について周知予定
〇 引き続き、がん患者が治療を受けながら働き続けられるよう、必要な支援に取り組む
前向きなご答弁いただきました。
これからも、がん患者が治療を受けながら働き続けることができるようさらなる支援をお願いして、次の質問に移ります。
【骨粗しょう症の検診の周知】
(検診の目的・必要性)
人生100年時代。100年歩ける足と骨づくりは、1日にして成らず。
特に、女性は、ホルモンの影響や妊娠などで大きく骨密度の低下を引きお越し易い状況です。
骨の強度が低下して、骨折しやすくなる骨の病気を「骨粗しょう症」といいます。骨粗しょう症により骨がもろくなると、つまずいて手や肘をついた、くしゃみをした、などのわずかな衝撃で骨折してしまうことがあります。
がんや脳卒中、心筋梗塞のように直接的に生命をおびやかす病気ではありませんが、骨粗しょう症による骨折から、介護が必要になってしまう人も少なくありません。
骨粗鬆症財団の調査によると、骨粗鬆症検査の受診率が低い地域ほど大腿骨の骨折を起こしやすく、介護が必要になる傾向が高くなります。
骨粗鬆症による骨折や要介護を減らすためには、骨粗鬆検査に力を入れることが重要であるとのことです。
先日、地元のお医者さんと意見交換をした際に、骨粗しょう症の検診率が極めて低い水準で、受診率アップの取り組みを求められました。
国が発表した令和6年度から開始された第五次国民健康づくり計画「健康日本21(第三次)」では、新たに「骨粗鬆症検診受診率」の目標を15%と掲げられました。
ところが、全国平均5・7%、都平均7%で目標を大きく下回る受診率です。
Q1,東京都の骨粗しょう症に対する認識と検診の取組を問う
A1
・ 骨粗鬆症は、骨折を引き起こし、寝たきりなどにつながるリスクを生じさせることから、予防が重要な疾患。
・ 早期に骨の量の減少を発見し、予防につなげるため、都は、健康増進法に基づく健康増進事業として区市町村が実施する骨粗鬆症検診を補助率3分の2で支援。
Q2, その検診の実施自治体数と受診者数、受診率について、令和6年度の実績を問う。
A2
・ 都内区市町村における令和6年度の骨粗鬆症検診は、37の自治体で実施されており、これらの自治体における受診者数は41,165人、受診率は10.5%。
Q3,4万人を超える方が受診されているとのことですが、未実施自治体が4割あります。また、受診率についても上げる必要があります。
例えば、対象年齢に受診券を郵送するプッシュ型で受診勧奨を行っている 港区、板橋区、目黒区等では、受診率は20%超えで国、都の平均を大きく超えていました。
自治体による検診実施や、こうした受診促進の取組を広げるべきであります。骨粗鬆症検診の実施自治体数の増加と受診率向上に向けた取り組みについて伺う。
A3
・ 都は、骨粗鬆症の発症予防及び重症化予防を進める上で重要となる、食生活、身体活動、飲酒、喫煙といった生活習慣改善の普及啓発を実施。
・ その取組を引き続き進めるとともに、骨粗鬆症検診を受診する機会を設け、受診できるようにするため、区市町村保健衛生主管課長会において、骨粗鬆症検診の重要性を周知し、実施を働きかけるほか、受診率の高い自治体の好事例を紹介するなど、検診実施区市町村の増加や受診率向上に向けて取り組んでいく。
【都立病院の経営】
(都立病院の役割)
地方独立行政法人東京都立病院機構は、東京都の医療政策として求められる行政的医療の安定的かつ継続的な提供をはじめ、高度、専門的医療の提供及び地域医療の充実への貢献等を推進することにより、都民の健康を守り、その増進に寄与することを役割としている。
都内で14病院とがん検診センターを運営する東京都立病院機構の2024年度決算が7月、明らかになりました。医業利益は2023年度よりも44億円改善したが、680億円の赤字で、負担金・交付金を繰り入れても当期利益は239億円の赤字で、2023年度よりも56億円悪化した。医業利益と当期利益のいずれも、全14病院が赤字。
Q1、都立病院の経営状況は、令和5年度は約183億円、令和6年度は約239億円の純損失と2年連続の赤字となり、厳しい軽状況と聞いているが、患者の受入は出来ているのか。
令和6年度に都立病院で受け入れた入院患者、外来患者の数について、伺う。
A1 (都立病院支援部長)
〇 都立病院全体の入院患者数は、令和6年度は延べ165万7,830人、
前年度の159万1,375人と比較すると、約6万6千人増加
〇 外来患者数は、令和6年度は延べ240万7,569人、前年度の240万127人と比較すると、約7千人の増加
Q2入院患者数、外来患者数とも前年度より増加しているとのことだが、令和6年度決算のうち、医業収支の状況はどうなっているのか、伺う。
A2 (都立病院支援部長)
〇 令和6年度は紹介患者の確保等に取り組み、医業収益は1,778億7千万円、前年度比で約79億円の増加
〇 一方、物価高騰の影響等により、医業費用は2,459億2千6百万円、前年度比で約35億円の増加
〇 医業収支比率は72%であり、前年度比で2ポイント改善
Q3、医業収支比率は改善しているものの、厳しい経営状況であることをふまえ、その課題克服に向けて、どのような取組を行ったのか。
適切な支出の徹底に向けた具体的な取組について、伺う。
A3 (都立病院支援部長)
○ 令和6年度より、DX関連業務 において、システムのバックアップ環境構築や
電子カルテ端末の設定作業等をベンダー委託から内製化に切り替え、約6.9億円の費用抑制
〇 診療材料については、国立大学病院等4団体と連携し、前年度比で約1億3,000万円の費用削減
○ 機構では、競争入札により交渉の相手方を選定して契約締結前に減額交渉を行う交渉権入札方式を採用。令和6年度は98件で実施し、入札価格と比較して合計で約1,900万円の削減効果
Q4、独法化したことにより、病院事業の特性に合った人材の確保が可能になったとのことであるが、具体的にどのような人材を確保できたのか、伺う。
A4(都立病院支援部長)
〇 独法化前、職員の職種の設定や採用については、条例等で統一的に定められていた。独法化により、医療ニーズや各病院の特性にきめ細かに対応した職の設定や採用が可能
○ 例えば、がんゲノム医療の遺伝子解析等を行うバイオインフォマティシャンや造血細胞移植に関する支援や調整等を行う造血細胞移植コーディネーターを新たな職種として設定し、駒込病院において活用。令和6年度は、救急救命士を新たに設定し、豊島病院等で活用
○ こうした取組により、医療の質の向上を図りながら、医療課題や患者ニーズに対応
【民間地域病院への支援について】
次に、民間地域病院への支援について質問します。
診療報酬が全国一律の中、人件費や物価高騰により資機材の高い東京の民間地域病院においては、令和六年度においては、約7割の病院が財政赤字を抱えています。
本来、国が診療報酬を地域の物価状況に合わせて加算すべきであります。
【質問の趣旨】
Q1,これまでも都が、診療報酬の見直しなどを国に要求するとともに、物価高騰対策を行ってきました。一方で、都内病院の7割が赤字との調査結果もあり、都として、国への更なる提案や支援の拡充が必要だと考えるが、今年度の都の取組について伺います。
【医療政策担当部長答弁骨子案】
〇 都は今年度、民間病院を対象に緊急的かつ臨時的に入院患者数に応じた支援金を交付
〇 また、都内病院等を対象に、地域医療に関する調査を実施
〇 この調査では、コロナ禍以降の患者数の減少や物価高騰等による経営状況の変化、他の地域との費用の差などを分析
〇 この調査結果を、国への更なる提案要求や都の医療政策の検討に活用
【薬物乱用ストップの取り組み】
薬物乱用問題は、全世界的な広がりを見せ、人間の生命はもとより、社会や国の安定を脅かすなど、人類が抱える最も深刻な社会問題の一つとなっています。
日本における近年の薬物情勢は、大麻の検挙者数が急激に増加しており、令和6年の大麻事犯検挙者数は依然として6,000 人を超え、覚醒剤事犯検挙者数と並んで非常に高い水準を維持しています。特に、若年層の大麻乱用が引き続き顕著で、30 歳未満の若年層が大麻検挙者の7割以上を占めています。
〇令和7年7月に厚生労働省が公表した「第六次薬物乱用防止五か年戦略」フォローアップによると、令和6年の大麻事犯検挙人員は過去最多であった前年より減少したものの、依然として深刻な状況である。とくに30歳未満の若年層の乱用増加に歯止めがかかっていない。
Q1、30歳未満の若年層における大麻乱用防止対策について、令和6年度の取組状況を伺う。
(食品医薬品安全担当部長 答弁)
A1
〇都は、薬物乱用対策推進計画に基づき、関係機関や地域団体と連携した啓発活動、規制や取締りなど総合的な薬物乱用防止対策を実施。
〇令和6年度は、大麻乱用対策に関する啓発動画を作成。薬物乱用対策を更に推進。
若年層の薬物乱用を防止するためには、学校における取組が極めて重要と考える。
Q2、都は小学校、中学校、高等学校が薬物乱用防止教室を実施する際にどのようなサポートを行っているのか、令和6年度の取り組み状況を伺う。
(食品医薬品安全担当部長 答弁)
A2
〇都は、小学校、中学校、高等学校等が開催する薬物乱用防止教室等について薬物専門講師を派遣。令和6年度の実績は、475件。
〇また、薬物乱用防止教室で使用するためのDVD等を貸し出し、令和6年度の実績は、398件。
文部科学省が行った「令和5年度における薬物乱用防止教室開催状況調査」の調査結果によると、令和5年度に薬物乱用防止教室を開催した学校について、小学校、中学校、高等学校のいずれについても、公立学校に比べて私立学校の開催率が著しく低い。
東京都内における令和5年度の公立全学校種の薬物乱用防止教室開催率は、小学校段階では 98.7%、中学校段階においては98.1%、高等学校段階においては94.5%と、全体で98.2%とほぼ100%に近い開催率となっています。
それに対して、都内の私立全学校種においては、小学校段階では 28.2%、中学校段階においては23.5%、高等学校段階においては28.3%と、全体で26.4%と、かなり低い開催率となっています。
この26.4%という数字は、私立全学校種の開催率として全国ワースト2位となっており、薬物の流通や蔓延が懸念される繁華街を多く抱える東京都では、子どもたちが薬物に関する正しい知識を十分に得られないまま、誤った誘いを受けるリスクが危惧されます。
このような背景において、私立の小学生、中学生、高校生が薬物の有害性について正しい認識をもつような機会が非常に低いという憂慮すべき状態があり、改善策が必要と認識いたします。
Q3 こうした状況をどのように認識しているのか、見解を伺う。
(食品医薬品安全担当部長 答弁)
A3
〇若いうちから薬物乱用防止教室などで大麻等の薬物の危険性を理解させることが重要。都は薬物乱用防止教室の講師派遣を実施。
〇都ホームページでの情報提供に加え、私立を含む小学校、中学校、高等学校に対しさらなる制度の周知。